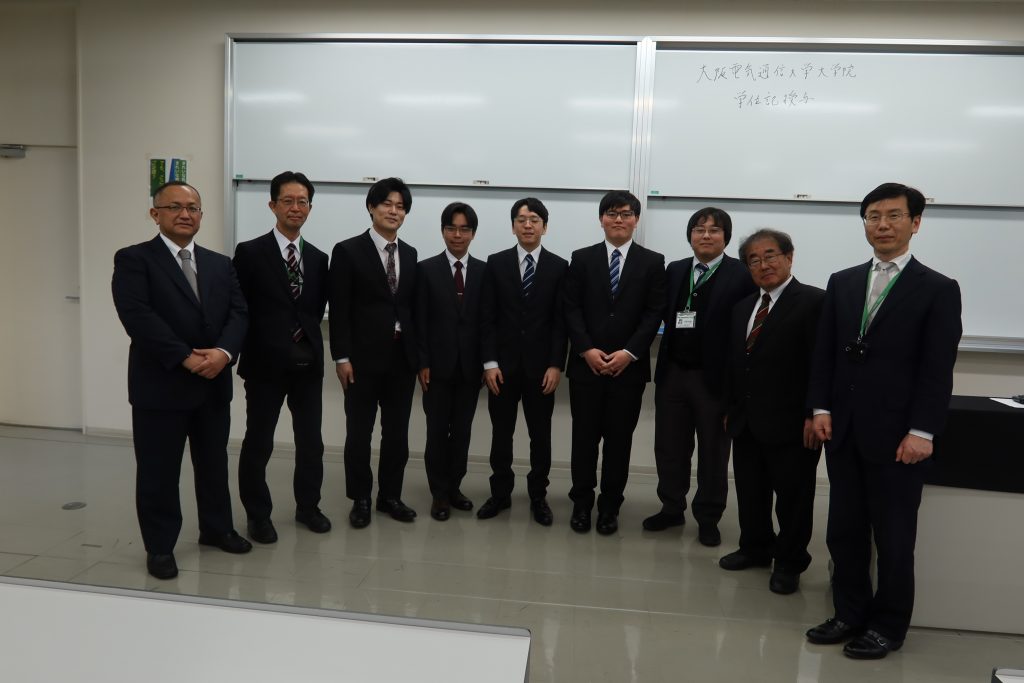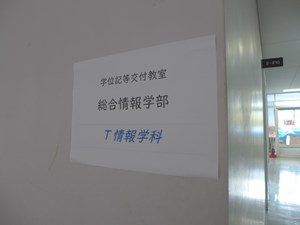2024年2月11日(日)に開催されたなわてんグランプリにて、情報学科から5名の学生が受賞しました。おめでとうございます!
「研究部門賞」
- 「RoboCup SSL Humanoid における歩行動作の選択の改善と複数キック選択のキックプレイへの応用」坂根 隆斗さん
- 「手の動きを用いた非接触インタラクション方法の検討」藤村 怜さん
- 「深層強化学習を用いた金融取引モデルにおける特徴抽出層の改善」中川 怜奈さん
- 「文化遺産のデジタルアーカイブのための点群データの設計値の抽出と軽量化に関する基礎的研究」小林 満里奈さん
- 「VR能体験システムの改善」佐々木 奏太さん
四條畷キャンパスの総合情報学部(情報学科、デジタルゲーム学科、ゲーム&メディア学科)では、卒業研究、卒業制作を一般展示する「なわてん」を毎年度開催しています。今年度は「なわてん Online(四條畷キャンパス 卒業研究・卒業制作展)」として、2024年2月3日(土)から3月29日(金)までオンラインにて開催するとともに、一部の展示については2024年2月10日(土)から2月11日(日)まで寝屋川キャンパスにて対面で開催しました。
なわてんグランプリでは、今年度のなわてんOnlineにて発表中の研究,作品から、審査の上優秀な展示が表彰されました。
なわてん Online (2024年2月3日~3月29日まで)
なわてん